業務内容
LGBT支援、同性パートナー支援

文書作成サポートのほか、社会生活でのお悩みについてご相談承ります。
●遺言書
自分が死んだときに同性パートナーに財産を遺すには、遺言書を作成する方法があります。
遺言書がないと、あなたの財産は法律で定められた親族が相続することになり、パートナーに直接遺すことができません。
●任意後見契約
将来加齢などにより、判断能力が衰えて、自分自身での社会生活が困難になった時のために、パートナーに財産管理をお願いする旨の任意後見契約書を作成しておくことができます。
正常な判断能力があるときに、任意後見契約を締結しておくことで、老後の備えになります。
●民事信託契約
自分の遺したいかたちで財産を遺していくために、信頼できるパートナーに財産を託しておくことができます。
●医療に関する同意書
急なケガや病気で意思表示ができないときに、どのような医療行為を希望するのか、また、その協議をする人として今のパートナーを指定すること、パートナーに病床で面会する権利を与えることなど記しておくことができます。
法律上の親族ではないからと、形式的に判断され辛い思いをしてしまうことのないように備えておくと安心です。
中国台湾人の相続、財産管理

日本に住む台湾人が亡くなった時の相続手続きについては、台湾の法律が適用されることがあります。
亡くなった人が帰化していれば、日本の財産については日本人と同様の手続きをしていくことになりますが、帰化前の戸籍について台湾からの取り寄せが必要です。
郵送で戸籍を取り寄せるには
①台湾在住の人(地政士など)に戸籍を集めてもらうため、台北駐日経済文化代表処で授権書に認証してもらう。
②授権書を台湾在住の人に送付し、戸籍を集めてもらう。
③集めてもらった戸籍に台湾の公証人の認証を受ける。
④外交部の認証を受ける。
⑤日本の台北駐日経済代表処で認証を受ける。
⑥日本語に翻訳する。
事例によって異なることもありますが、現在では認証の手続きは不要とされていますので、個別に対応します。
いずれの場合でも、手間と日数がかかるのは仕方ありません。
台湾民法では、相続人、相続分、遺留分など、日本民法と異なりますので、亡くなった人の国籍、財産によって個別に判断して手続きをします。
中国人についても、中国法を適用するケースと、日本法を適用するケースがありますので個別に判断します。
また遺言書を作成するときにも個別に注意が必要です。
公正証書作成支援

●保証意思宣明公正証書
これまで具体的な主債務の内容について十分に理解しないまま保証契約を締結してしまい、保証人が生活の破綻に追い込まれるということがありました。
そこで、保証人保護のため、事業用融資の保証契約をする時、一定の条件に当てはまる場合、契約の1月前以内に保証意思宣明公正証書を作成しなければなりません。
保証人となる予定の人が、自分がどんな内容の保証契約をするのか、きちんと理解しているということを、必ず公証人の面前で証明し、公正証書にします。
作成には、金融機関等で一定の書類を用意してもらい、公証人との事前準備と予約が必要です。
●公正証書遺言
公正証書遺言を作成する利点は、
①方式不備により無効になったり、解釈の疑義による紛争のおそれが少ない。
②原本は公証役場で保管されるので、紛失、隠匿、変造の危険がない。
③検認が不要である。
どの財産をだれに遺したいのか、他の遺言書と抵触していないか、遺留分に配慮しているか、遺産分割の余地を残すのかなど、最終意思が実現できるように準備し作成します。
●離婚公正証書
協議離婚をするときに、財産分与、養育費、慰謝料など離婚の条件を決めた場合、公正証書にしておくと、のちにどちらかが約束違反をしたときに、条件どおりの履行の請求をしやすくなります。
離婚公正証書は、どちらか一方のみで作成することはできません。離婚に至った経緯、財産の状況に応じた養育費の支払いなど、作成前に納得いくまで話し合いと準備が必要です。
成年後見

●認知症になった親の不動産
高齢の親が認知症になり、介護のための施設入所費用などを、親の不動産を売って捻出したい場合でも、子らの判断で親の不動産を売却することはできません。たとえ親のためであったとしてもです。
その場合、成年後見人が、認知症になってしまった親の代わりに、売買契約を締結する方法があります。
成年後見人とは、判断能力がない人に代わって財産管理など、様々な法律行為をする人で、近くに住む親族などがなる場合と、司法書士などの専門職がなる場合がありますが、いずれにしても、家庭裁判所に選任の申立てをし、就任してもらいます。
そして就任した後見人は、本人に代わって不動産売買取引をするのですが、準備に手間と日数を要するので、施設入所までのスケジュールには注意が必要です。また、親の居住用不動産を売却する場合は、裁判所の許可が必要になります。
後見人は、一度の不動産売買契約だけのために就任するのではなく、その後も引き続き、本人に代わって法律手続き、財産管理、療養看護などをしていきます。
●親が死んだので遺産分割協議をしたいが、子の一人に知的障害がある
障害の程度にもよりますが、判断能力がない人は遺産分割協議をすることができませんので、 成年後見人が本人に代わって本人のために他の相続人と遺産分割協議をすることになります。
その場合、障害のある本人に不利益になる協議はできないので、少なくとも法定相続分は本人が取得するような協議でないと応じることができないと思われます。
この場合、兄弟などは利害関係人なので成年後見人として遺産分割協議をすることができないので、司法書士などの専門職が成年後見人になるケースが多いです。
土地・建物の登記

●親族が亡くなったときの相続登記
●土地や建物の贈与登記
●土地を買った時
●家を新築したときの所有権の登記
●住宅ローンを組んだ時の抵当権の登記
●住宅ローンを完済した時の抵当権の抹消の登記
会社の登記

●会社設立の登記
●役員の変更、任期更新の登記
●会社の名前や事業目的の変更登記
●各種法人(学校法人、医療法人、NPO法人、社会福祉法人)の登記
財産管理
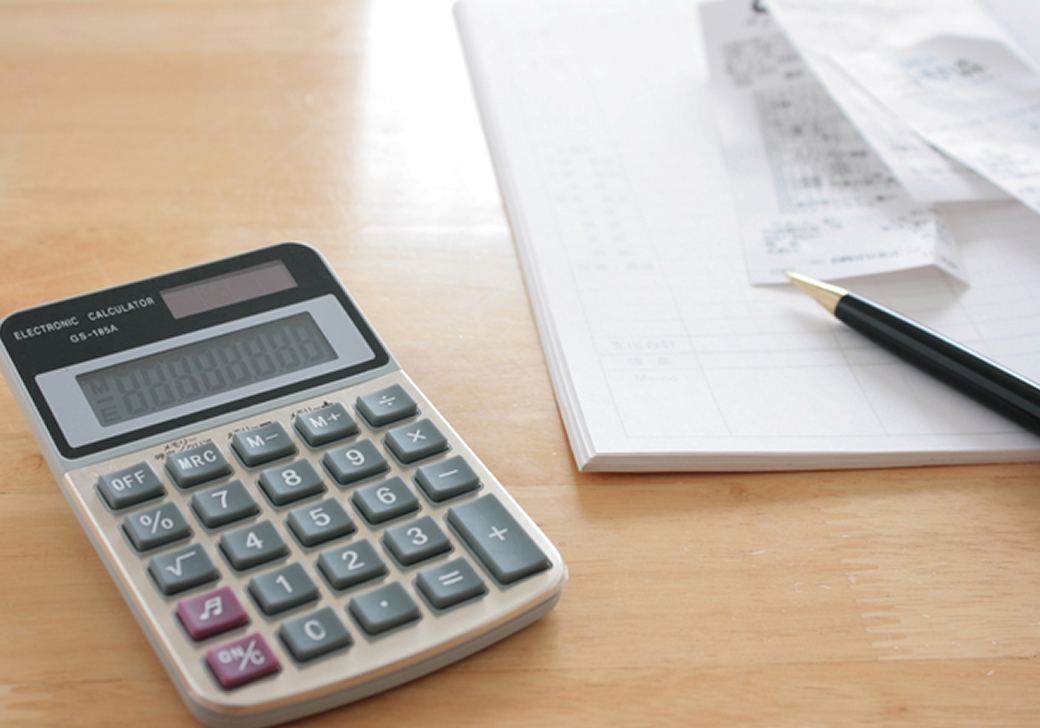
●親族が行方不明で、連絡がとれない、生きているのかもわからない
●自分には相続人がいないが、財産はどうしたらいいのか
●遺言書を作成したい
日常生活のトラブル

●夫からDVを受けている
●離婚したい
●別れた配偶者が養育費を払ってくれない
●エステの契約を解除したい
●父の相続財産の遺留分減殺請求をしたい
●借金の返済ができない
裁判所提出書類の作成

●相続放棄をしたい
●遺産相続でもめているので、調停を申し立てたい
●裁判の訴状を作成してほしい
●亡くなった父が自分で書いた遺言書を見つけたので、検認の申立てをしたい




